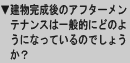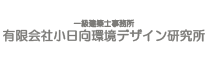
「資金計画」「融資交渉」「敷地の選定」「設計者の選定」「建物の設計」「役所への申請手続き」「建物のビルダーの選定」「建物の建設」
これらの全てにおいてお客様が陣頭指揮を執っていかなければならないことはご承知かと思います。
ご安心ください。私達が豊富な経験と情報、高い技術をもって、お客様を最初から最後までサポートをさせていただきます。それぞれの場面で専門のパートナーが適切な役割を果たします。
⇒ 当事務所がサポートします。
始めにお客様がどのようなライフスタイルを希望されているかをご家族で話し合って明確にすることが重要です。
「家族団欒を第一番に考えたい」「休日には料理を家族と一緒につくりたい、」「趣味ができるコーナーが家族それぞれにほしい、」「友人や親戚関係を家に呼んで深めたい」「自然環境を家の中に取り入れたい」「子供と会話のできる家」「音楽がいつも流れている家」「バリアフリーを考慮した永住したい」「家族構成が変化しても対応できるようにしたい」「好きな絵を見て暮らしたい」等、より具体的にすることにより夢が現実となります。
私達はそれに必要な空間作りをしていくことがお客様の夢の実現にもっとも近い建物が完成すると考えています。
⇒ 当事務所や各専門のパートナーがサポートします。
土地代、土地の登記費用、敷地測量費、既存建物解体費、地盤調査費、地盤改良費(地盤が悪い場合)、設計監理費、各種申請料、建物建設費、完了検査費(検査機関検査)水道引込負担金、下水道負担金、外構工事費、カーテン・ブラインド代、建物登記、
これらを全てお客様一人で予算建するのは困難です。不動産屋、設計士、ビルダー、税理士の専門家の助けが必要です。
そして、融資先の金融機関との交渉もお客が中心で行ないます。ご安心ください、私達専門家が各段階でサポートさせていただきます。
⇒ 建築設計専門の当事務所がサポートします。
診療圏内の調査の情報をもとに不動産業者から希望されている地域内のいくつかの敷地の候補が上がってきます。
そして適切な敷地を選定するために敷地の調査を行う必要があります。
現地調査では医院開業に適している敷地であることはもちろんのこと他に重要なポイントがいくつかあります。法律的な条件の調査、インフラ(電気、ガス、上水道、下水道)の整備状況調査、道路の接道調査、隣接する敷地建物の調査、地盤の調査(事前調査程度)、道路の交通状況調査これらの調査は建物を建設する上で重要な調査です。
チェックポイントの詳細は無料進呈中の「敷地を選定するときの6ポイント」をご覧ください。
不動産業者は、建物を建てる専門家ではありません、大まかな知識はありますが十分ではありません。また土地の売買だけを目的に「売ってしまえば・・・。」と考えている不動産業者も多くおります。
当事務所の経験でもお客様が事前に購入された土地で不動産業者の知識不足で設計時にインフラ整備の問題で苦労したことがございます。
敷地を選定する前に必ず建築設計専門家の調査、アドバイスを得ることをお勧めいたします。当事務所は、豊富な経験をもって調査を行い、適時、適切なアドバイスをお客様に提供しサポートいたします。
お客様の希望する条件がそろった敷地が見つかった時点で最終的に敷地を決定する場合にも事業計画書で予算立てをした内容を確認し、敷地の価格交渉をいたします。
⇒ 当事務所が事前に各作業ごとの分かりやすい見積書を提出いたします。
当社の「設計・監理の進め方」をご覧になっていただければその内容と丁寧さがご理解いただけると思います。当社では各作業ごとの分かりやすい見積書を提出しております。
⇒ 当事務所がサポートします。
⇒ 当事務所がサポートします。
一つ目は信頼できるビルダーを1社指定する方法と二つ目は3社程度選択し競争入札する方法です。
お客様のご希望によってどちらの方法も可能です。
ただし、競争入札の場合のデメリットもあります。品質を下げないでコストダウンする方法や今後メンテナンスで長くお付き合いすることを考えると前者をお勧めいたします。
詳細は、お役立ち情報をご覧ください。 いずれの決定方法においても地元の信頼できるビルダーをお勧めいたします。
もちろん大手メーカーや大手建設会社にお願いすることも選択肢の一つですが、価格やアフターメンテナンスのことで判断するとやはり地元ビルダーにはかないません。
この時点で私どもは、お客様の立場でビルダーから提出された見積書の価格、数量等が適正かの査定を行いお客様にご報告しサポートいたします。
また、ビルダーの過去の実績を見学し、仕事の仕上がりも評価の一つとする必要があります。「安かろう、悪かろう」では、後でお客様が損をすることになります。
⇒ 当事務所がサポートします。
工事期間中は、週に1度の頻度で私達専門の設計者が工事を監理いたします。
実施設計に基づいて各工事の仕様、品質、施工精度、構造をビルダーと共に逐一検査していきます。
⇒ 地元ビルダーがサポートします。
一般的には、平成12年より施行された「住宅の品質保証の促進などに関する法律(品確法)」により、建設を行なったビルダーは新築住宅の引渡し日から10年の間、住宅の「基本構造部分」に瑕疵が発生した場合、その発生した瑕疵を無償で補償または損害補償しなければなりません。
法律的な瑕疵保障だけでなく建物のアフターメンテナンスのサポートは建物を長年価値あるものとして維持していくにはとても重要なことです。残念ながらビルダーによって格差があります。信頼がおけてアフターメンテナンスに実績のあるビルダーを選定することをお勧めします。
ハウスメーカーは、新築の売り上げ重視でアフターメンテナンスの評判はあまり良くありません。
一方長年続けている地元ビルダーにとっては、将来の改装、改築も大切な仕事の一部ですので当然クライアントとの良い関係を長く続け、将来の仕事のつなげることを考えています。従って問題があればすぐに駆けつけてくれるビルダーがいます。