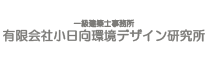
かつて、戦後の建設ラッシュ時の日本の建設業界の多くのビルダーの意識の中には、工事の手間賃(工賃)より建材、資材のほうが高いという意識がありました。今でもその意識は残っています。「手間をかけてもいいから材料を無駄にするな!」と盛んに親方から怒鳴られながら教えられ育った職人さんが多くいます。
しかし、現在は建材、資材よりも人件費の割合が高くなっています。
材料費と工賃の割合がアメリカでは、1:1であるのに対して過去のわが国では、1:2~2.5という状態になっていました。これらの数字から判断してもいかに工賃を無駄なく、合理的に建設することがコストダウンにつながるかが理解できると思います。現在でもビルダーの中にこの意識が多少なりとも残っています
バブル崩壊後価格競争の波により建設業も必然的に合理化を目指さなければならないことになりました。必然的とはいいながらもビルダーが無駄を省き、工期短縮を真剣に努力した結果、建設業界全体の工事費のコストダウンが行われました。
しかし、現在はさらにコストダウンするためにグレードダウンと同時に手間抜きの領域にまで入り込んでくる危険性が感じられます。品質を下げずにコストダウンするためには、設計から工事完成まで間で「無駄をなくす」という一貫した合理化が大きな要素となります。
はじめに施主の希望に無駄がないかを建築家と共に整理する必要があります。
特に無駄な開口部、収納スペースは、全体的にコストアップにつながっていきます。(知人の奥さんが、とにかく明るく開口部の多い空間がほしいとの条件で建物が完成したそうです。現在その家は夏場には室内が暑く、昼間でも開口部の多くがカーテンが引かれたり雨戸が閉まったままクーラーがガンガンかかっていると知人からきかされました。・・当社の設計でありません。)
また、日本人の家に所有する生活必需品は、アメリカ人の2倍近いときいたことがあります。収納があれば物が増えていきます。
当社が設計に着手する前に施主にたいしてお聞きすることは、「どんな生活をしたいか?」を具体的におうかがいします。漠然としているとあれもこれも大きめに、多めにということになります。
次に設計時では、材料や手間を無駄にしないように考えて設計を行います。
企画寸法の製品は量産されてコストも安いのは当たり前のことです。構造部材からタイルなどの仕上げにいたるまでなるべく企画寸法の製品で収まるように設計し、カットする材料、手間をなるべく減らすことです。
姉歯事件のように材料を間引きすることでなく一つでも無駄な作業を減らす積み重ねが大きくコストカットにつながっていきます。
工事中は、十分に検討された設計図を基本に職人さんたちの作業効率をいかに高めるかが、地元ビルダーの力量によるところであります。業界では段取りの良し悪しといわれています。工程、段取りの組み立て次第によって大きくコストに影響します。
したがって、段取りの良い現場担当者を確保することが重要です。
さらに付け加えると「作品となる良いものを作ろう」という意識が設計者からビルダーそして各職人さんたちにいかにいきわたるかによって品質の良い建築物ができあがります。
バブル崩壊後の価格競争が年々激化する中で総体的に建設費は確かに安くなっています。住宅の坪単価も30万円を切る数字も広告で見るようになりました。
建設業界では、工事の合理化を考えたコストダウンの努力も限界を超えているといわれています。ビルダーは、マイナスであっても受注してしまう工事も多く見られるようです。
ビルダーにとっても死活問題ですのでマイナスを出さないような方法をとります。
コストダウンの簡単な方法としては、建物のグレードダウンが考えられます。施主に見えないところでグレードダウンを図る。
社会問題になった姉歯の問題がその実例です。
また、某ビルダーは、雨が降ろうが工期短縮のために本来行ってはならない工事を進めてしまい入居後、カビ、錆びの発生により問題になっている住宅もあります。
職人さんにランクがあるのはご存知ですか。
たとえば、大工さんにも腕の良い人、悪い人がいるのはご承知だと思います。
本来、一人前の腕の良い大工さんになるための修行は8~10年かかるといわれています。
バブル期に建設物件が多くなり大工さんの数が不足している時期でもあり、3~4年の修行で独立する大工さんが増えたといわれています。
当然腕の良い大工さんは引っ張りだこで手間賃が高いし、悪い大工さんは手間賃が安くなっいきます。
他の職種も同じようにランクがあるようです。当社が、仕事をビルダーに発注するときは、要となる職人さんを指定するか、メーカー及び職人さんのリストや経歴確認します。必要とあれば過去の仕事を見させてもらいます。
大手建設会社の同じ会社内であっても担当する所長の違いによって大きく建物の出来が違ってきます。
異常なコストダウンの建物にはかならず仕掛けがあります。(当社で住宅相談会を行っていたとき30代の男性が相談にこられました。3年前に家を建てたのだがコストを押させすぎたせいか内装の床が劣化したり、壁紙がはがれはじめ内装をやり変えたいとの相談でした。3年で内装をやりかえることは異常な状態ですが現実的に多くの場所で起こってきているのではないでしょうか。)ご注意を!!
必要であれば立地条件の調査(医院の場合は市場調査も含め)を行ったり、設計作業時に建築家と地元ビルダーとの検討を重ねることにより、無駄な設計や材料の無駄、合理的な工法を探し出すことが可能になり、工事スタート時点から速やかに建設が可能になります。
基本設計完了時には、地元ビルダーが概算見積を行います。もし予算がオーバーしているのであらば、基本設計の見直しを行ってから次の実施設計の作業に取り掛かります。
基本設計後に概算見積を行わず実施設計が完了していざ本見積が出てきたときに大きく予算オーバーしてやり直しになるケースもよくあるとききます。
パートナーシップの場合は、このようなやり直しで無駄な作業をすることはありません。
信頼のおけるビルダーを選定するのですから技術力をよく理解して仕事を任せられます。建設作業は、いかに適切に内容を伝えられるかが重要です。
技量を知らない同士が行うと決して良い建物はできないのです。
又、建物は施主、建築家、地元ビルダー、職人の多くの人々がかかわって一つのものを作り上げていくのですから同じ土俵にのってそれぞれの立場で肯定的なディスカッションをすることが良い建物を作る条件の一つです。
建物にはアフターメンテナンスが、重要です。設計時から参加している信頼のおける地元ビルダーこそが適切にアフターメンテナンスの対応をしてくれます。地元ビルダーだからこそできることです。
建設時のコストは確かに安くしたいのですが、安易に安い材料を使用したり、安易な施工をしてしまうことによりメンテナンスのコストが高くついてしまうことがあります。(当社で住宅相談会を行っていたとき30代の男性が相談にこられました。3年前に家を建てたのだがコストを押させすぎたせいか内装の床が劣化したり、壁紙がはがれはじめ内装をやり変えたいとの相談でした。3年で内装をやりかえることは異常な状態ですが現実的に多くの場所で起こってきているのではないでしょうか。)
外装仕上の塗装、屋根の塗装の塗り替え、内装仕上げのクロスの張替え、設備機器の取替え、など10年、15年ごろから必要に迫られます。
メンテナンスコストの中でも仮設費用は、意外とかかってしまいます。従って多少材料代が高くてもメンテナンスの回数を減らすことは効果的な方法です。建設時にはライフサイクルの視点で材料の選定をすることをお勧めいたします。
はじめに車椅子対応として敷地内から院内の床の段差をなくすことです。
スロープの設置、出入り口の段差をなくすことによりスムーズに通行が出来るようにすることです。エントランスの入り口は、自動扉か、引き戸とします。
上下足の履きかえを無くし院内の床は土足とすることをお勧めします。
また、スリッパの衛生面や管理は既存の医院の一つの悩みとなっています。
診察室の扉や処置室の扉も引き戸をお勧めします。待合室には車椅子用のスペースと用意します。受付に近く、出来れば一番良い位置を確保することにより医院の細かい配慮を患者様に感じていただけます。
扉の幅も車椅子の幅を配慮し寸法を広くとります。
高齢者対応の一つにサイン計画をわかりやすくすることです。室名を大きくしたり目的の違う扉の色を変えることなどを当事務所では実施しています。